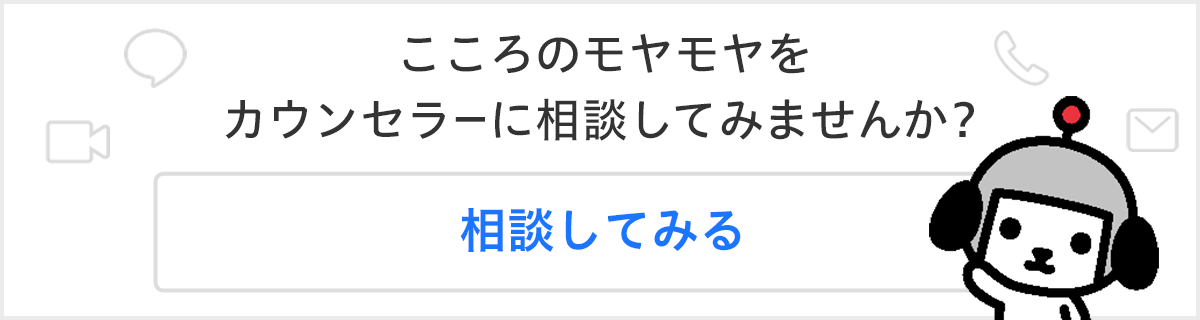ベストアンサー
京都にある東本願寺、西本願寺は、いわゆる通称というものであります。 西本願寺は正しくは龍谷山本願寺といい、浄土真宗本願寺派の本山です。 一方、東本願寺は正しくは「真宗本廟」といい、真宗大谷派の本山です。 戦国時代、石山合戦で一向宗(本願寺派)の本山である石山本願寺(現在の大阪城がある場所にあった)が、武装解除に応じたことで、一向宗は石山本願寺から追われます。 秀吉の治世になり、本願寺派は京都の烏丸で本願寺の再興を許されます。 その後、家康の宗教政策によって、当時、本願寺内で分裂状態が起きていたことを利用し、 教如を門主とし、本願寺のすぐ東の土地を与えられ本願寺を分立したのが真宗大谷派の始まりです。 この本願寺の立地関係から、西と東という通称が付けられるようになったのです。 そのため、本願寺派と大谷派の違いは、政治的問題によって分裂が起きたのですから、教義上においてはほとんどありません。 それゆえ、東西の交流がもどるのもさほど時間はかかりませんでした。 (日蓮系宗派が教義上の理由で分派している点とは大きな違いです。) せいぜい、本願寺派中興の祖、蓮如上人の五帖御文の呼び方が、本願寺派が「御文章(ごぶんしょう)」といい、大谷派が「御文(おふみ)」ということ、日常の勤行で読まれる「正信念仏偈」の節回しが微妙に違うこと、「南無阿弥陀仏」が本願寺派では「なもあみだぶつ」に対して大谷派では「なむあみだぶつ」と唱えます。 あと、焼香の回数が本願寺派は1回、大谷派は2回。お仏壇の様式が微妙に違うところがあります。 まぁ、その程度の違いしかないのです。 ちなみに、浄土真宗西本願寺派という呼び方は誤りですし、またそのような宗教団体はありません。 また、真宗東本願寺派というのはありませんが、浄土真宗東本願寺派という宗教団体はあります。 これは、昭和56年に宗派の維持・運営をめぐる見解の相違により、真宗大谷派から離脱・独立した宗派で、東京にある「東本願寺」が本山です。 私信として・・・shamosikaさんへ ハト派→本願寺派、タカ派→大谷派・・・妙に納得してしまいました。 まさに、shamosikaさんと私の性格の違いが出ているような^^;
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
質問者からのお礼コメント
詳しいご説明ありがとうございました。よくわかりました。
お礼日時:2011/1/28 21:38
その他の回答(4件)
本願寺法主顕如氏の三男がついだ「戦国抗争へのハト派」「親豊臣」の性質をもつ本願寺本家筋から始まったのが【本願寺派(本山通称:西本願寺)】 本願寺法主顕如氏の長男が新たに建てた(分家)、「戦国抗争へのタカ派」「親徳川」の性質をもつ本願寺法主嫡流になるのが大谷派・・・その本山通称が東本願寺 念仏が「無間地獄堕ち」と考えたのは、日蓮聖人独自のお考えです。法華経では念仏は「無間地獄堕ち」などとは一切言っていませんので、心配なく。
東本願寺派 wikiからです。 教義上の解釈や宗派の運営方針等をめぐって保革が対立し、紛争に及んだ(お東騒動)。これによって大谷派から分裂しました。
東本願寺=大谷派の総本山 西本願寺=本願寺派の総本山 戦国時代まで本願寺は一つで親鸞の子孫が住職(宗派の最高指導者)を務めていましたが、一向一揆の方針をめぐって兄の教如(抗戦派)と准如(和睦派)が対立し、教如は豊臣秀吉の命令で本願寺を追放されました。のちに徳川家康が一向一揆の再発を防ぐため、両者の対立に便乗する形で教如を支援し、もう一つの本願寺を造らせました。准如の流れを汲むのが西本願寺、教如の流れを汲むのが東本願寺です。 両者に教義上の違いはありません。現在は「真宗教団連合」を結成して相互交流を行っています。