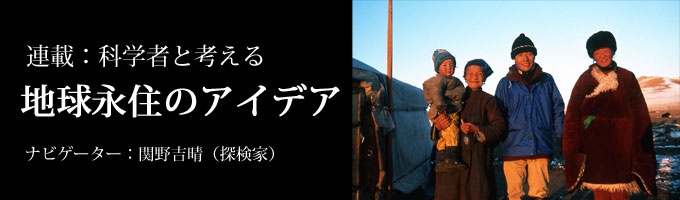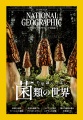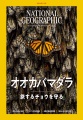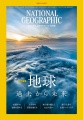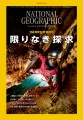第6回 海部陽介(人類学):人類はどのように日本列島にやって来たのか?(提言編)
ホモ・サピエンスはなぜ世界中に分布しているのか? 日本列島へやって来た祖先たちはどのようにして海を越えたのか? 国立科学博物館人類研究部人類史研究グループ長で、3万年前の航海徹底再現プロジェクト代表の海部陽介氏に、2019年夏に丸木舟で台湾から与那国島を目指す航海実験について語っていただきます。
こんにちは、海部です。
ぼくは、人類が約700万年前にアフリカで誕生してから、どのように世界中に拡散して暮らしてきたのか、つまり人類の歴史を知ることが、地球永住のヒントになると考えています。
まず、過去に登場したさまざまな人類の中でホモ・サピエンスだけが世界中に広がった理由を考えてみましょう。
ホモ・サピエンスはなぜ世界中にいるのか?
ぼくらとサルの違いのひとつは、生息地域です。霊長類は200~300種いますが、どれも限られた地域にしかいません。でも、ホモ・サピエンスは1種で全世界にいます。ぼくらは世界中に人間がいるのはあたり前だと思っているけれど、生物学的にいうと全然あたり前じゃないんです。なぜそうなったかというのが、ぼくのひとつの大きな疑問です。
15万年前の世界を見てみると、ホモ・サピエンスはアフリカだけにいて、ユーラシアにネアンデルタール人(旧人)がいて、中国に旧人がいて、インドネシアには原人がまだ存在していました。その時人類は多様だったんです。これは生きものとしては普通の状態です。では、どのようにして今のような地理分布になったのでしょうか。
185万年ぐらい前に、原人のグループがアフリカの外に出たことがわかっています。この人たちがジャワ原人や北京原人になっていき、またフローレス島などにも到達しました。こうして人類は多様化していきました。
私の地球永住計画
遺跡を発掘し、出てきた人骨化石や文化遺物を調べ、過去数百万年におよぶ人類史を復元する研究を続ける中で、祖先たちのことを大きく誤解していたことに気づいた。例えば、「昔の人たちは自然を大切にしていた」というのは、半分幻想だ。そうであったなら、マンモスもナウマンゾウも絶滅はしていなかったろう。一方で、大昔の人の“原始人”というイメージも、素朴すぎる。なぜなら彼らは、海や酷寒の地という障壁を乗り越えて、アフリカから世界中へ大拡散するだけの何かを持っていたのだから。
そうして始まったホモ・サピエンスの歴史が、今、新たな局面を迎えている。経済格差、差別、食料・資源の危機、大規模戦闘、環境破壊と、暗い要素には事欠かない。これらを乗り越えて、平和共存の未来をつくりたいのなら、人間と自然に対する、過不足ない、適切な認識と理解が必要になる。その意味で、私は祖先たちへの誤解を解く研究を続けて行きたい。そこに、ホモ・サピエンスを理解する鍵があるように思えるから。
海部陽介
「科学者と考える 地球永住のアイデア」最新記事
バックナンバー一覧へ- 第6回 海部陽介(人類学):人類はどのように日本列島にやって来たのか?(対談編)
- 第6回 海部陽介(人類学):人類はどのように日本列島にやって来たのか?(提言編)
- 第5回 小泉武夫(醸造学・発酵学・食文化論):発酵は世界を救う(対談編)
- 第5回 小泉武夫(醸造学・発酵学・食文化論):発酵は世界を救う(提言編)
- 第4回 中村桂子(生命誌):人間は生きものの中にいる(対談編)
- 第4回 中村桂子(生命誌):人間は生きものの中にいる(提言編)
- 第3回 宮原ひろ子(宇宙気候学):宇宙からの視点で地球の住み心地を考える(対談編)
- 第3回 宮原ひろ子(宇宙気候学):宇宙からの視点で地球の住み心地を考える(提言編)
- 第2回 山極壽一(霊長類学):サル、ゴリラ研究から現代社会を考える(対談編)
- 第2回 山極壽一(霊長類学):サル、ゴリラ研究から現代社会を考える(提言編)