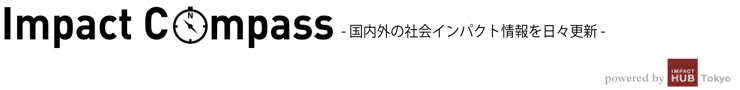「来週から長野県に住むから。」 私がImpact HUB Tokyoで働き始めた日、経営者から言われた言葉だ。 これまで通り経営にコミットをしつつ、自身の生活のことを考えて決めた結果だという。 私は仕事を始める間もなく、頭をガツンと殴られたような衝撃を味わった。
Impact HUB Tokyoに転職が決まった私は、職場まで自転車で通える部屋に引っ越した。これで好きなだけ仕事ができる、満員電車とも無縁な理想の生活を手に入れた、と思っていた私にとって、経営者の移住の知らせは驚きの一言だった。
それから一年が経つ。だが、その時に味わった衝撃は、日々向き合うべき、自分自身への問いへと変わった。それは、「プロフェッショナルであることの証とは、24時間、仕事のことだけを考え、動き続けることなのか」という問いだ。
これまでのキャリアの中で、ごく当たり前のものとして受け入れてきた、過去のプロフェッショナル像が揺らぎ始め、消えない疑問として渦巻き始めている。おそらく、ミレニアル世代と呼ばれる私たちの世代の多くが、同じ疑問を抱えているのではないか。
プロフェッショナルとは何か?
そもそもプロフェッショナルという言葉を聞いて、私たちはどのような人を連想するだろう?専門領域で一流の評価を得て、自分の名前で仕事をしている人を思い浮かべる人もいれば、期待を絶えず越えるパフォーマンスを追求する、弛まぬ努力こそがプロフェッショナルだと考えている人もいるかもしれない。巷の本屋で陳列された、仕事論を説く本の数々を眺めていても、世の中では、多くの「プロフェッショナル論」が紹介されている。
私の場合、「プロフェッショナルとは何か?」という問いかけは、学生時代の模索から始まった。学生として学び、自身の将来を考え始めた頃、一番近くで見てきた両親の仕事、サークルやゼミの先輩の就職先、といった世界だけが、プロフェッショナル像を考える手がかりだった。
まだ働くという実体験を持たない学生時代において、プロフェッショナル像を描く探求は、どうしても空回りしがちだ。その過程は「自身は何者か?」という悩みと切り離せない。「社会に出る」という人生の一大イベントが目前に迫る中で、両親とも友人とも違う、固有の自分とは誰なのかと思い悩み、もがき続ける。
その後、実際に社会に出て働き始める中で、多くの場合、全く何もできない無力な自分を見つけることになる。仕事のイロハを身につけ始めるために必要なのは、ちっぽけな自分の目標やプライドを捨て去ること。目の前の一つ一つの小さな仕事に没頭しながら、時折、自分の学生時代の目標を忘れはしないか、という不安に駆られながら最初の数年間を過ごし始める。
今までロールモデルとされてきた「プロフェッショナル像」への違和感
まだ働き始めて間も無い20代が、仕事で壁を感じて相談相手を求める時、そのロールモデルを一つ上の世代に求めることが多いと思う。例えば、30代で実績を積み始め、多くの人から評価を集めて、自信に満ちた魅力を放つ人たち。 その相談相手が、20代の時に、どのように毎日を過ごしていかを聞いてみると決まって、「毎日がむしゃらに深夜まで働いていた。それが誰にでも必要な、通るべき道だ。」という答えが返ってくる。それくらいに没頭して、初めてプロフェショナルとしてスタートラインに立つことができるものだ、と諭される。「やはり、そういうものなのだ」と私たちは納得し、毎日の職場に還って、仕事に励む。その先に描く、憧れのプロフェッショナル像を追いかけて。
「まずは全力で走り続ければいい。スピードを緩めることはいつでもできる。20代の猛烈な努力があってこそ、初めて緩める、という選択肢が与えられるのだ。」いろいろな人の話を聞いて、私が認識したのは、そういうメッセージだった。
そして、「それは、後から理解し、語られるべきことだ。」そのように言い換えることもできるかもしれない。
結局、プロフェッショナル像を、自身の価値観で選び取り、創りあげることは、実に困難なのだ。学生時代の仕事経験を伴わない思索は、なかなか深まることはない。さらに、働き始めて、仕事のイロハを学び始めるひよっ子の状態においても、根本的な問いを深めていく余裕は、なかなかない。悩んでも、仕事に没頭しても、依然としてプロフェッショナル像は遠い存在であり、その結果、周囲にいる従来のプロフェッショナル像に強い影響を受けながら、毎日仕事をしていることにすら、なかなか気づくことができなかった。
新たなワークスタイルの出現
しかしながら、ふと目を横に向けると、どうだろうか?ミニマリズム、移住、マインドフルネス、といったムーブメントが若い世代の心を広く捉えている。
それは特に、「ミレニアル世代」と呼ばれる、2000年代に成人した世代に顕著な動きだ。ユースカルチャーに根ざしたライフスタイルの志向、社会への関心の高さ、性別間の役割分担意識の薄さが、ミレニアル世代に象徴的な特徴と言われる。
日本でも、10年ほど前から、ソトコトやgreenz.jpといった雑誌が新たなワークスタイルを提唱してきた。ここ数年、その動きがさらに派生し、人とモノとの関係性、住む場所や食べるものへの意識、東洋思想の内省への再注目へとつながってきている。
また世界に目を向けてみても、ポートランドのKinfolkのような雑誌が、若手クリエイター向けに新たなワークスタイルを提唱して、ミレニアル世代の多くの支持を集めている。
源泉に向き合うことのできる「プロフェッショナル」のあり方
こうしたムーブメントは、単なるカウンターカルチャーとしてではなく、多くのビジネスパーソンへの広がりを持った世界的な動きとなってきた。それは、「学習する組織」のピーター・センゲや、「U理論」のオットー・シャーマーといった、ビジネスの世界に影響力を有する経営学者が、内面的な世界の重要性を強調し、内省を促してきたのにも見て取れる。
オットー・シャーマーが、ピーター・センゲにインタビューを行った際の最初の質問は、「あなたの仕事の根底にある問いは何ですか?」だった。彼らは、一人一人が、自身の深い意図と結びつき、心から大切にしたいと思うものを自覚する重要性を強調する。
「あなたの行動の起点は、どういう源(Source:ソース)から生じているか?」と、彼らは何度も問う。私はこの流れを見ながら、確信する。やはり、従来のプロフェッショナル像は、行き詰まったのだ。
右肩上がりの世界観はもういらない
確かに世界は、猛烈に働くプロフェッショナルたちの途方もない努力と献身の上に成り立っているように見える。だが、内面的な探求を軽視してきた結果、うつ病などの精神的な問題、家族との関係の行き詰まりなど、様々な歪みが社会問題として見て取られることは、否定できない。
様々なシステムが淀みなく整然と機能する世界で、私たちは日々生産と消費を繰り返して生きている。美しいライフスタイル雑誌を手に取ると、そこに並ぶのは高価なブランド商品を輝かしくまとった広告モデルたちだ。ワークスタイルだけでない、ライフスタイルにおいても同様に、「拡大」と「上昇」を志向する。家族は仕事の延長として、「家族サービス」などと言い換えられる。
しかし、そんな右肩上がりを前提とした世界観は、沸点を超えて蒸発し始めているのではなかろうか。
家族やパートナーの関係の中にある「プロフェッショナル」
そもそも私たちの人生は、一人だけの物語ではない。家族の犠牲を伴う、偽りのプロフェッショナルの成功ストーリーはもういらない。夫婦であれば、二人のパートナーシップの物語。子供がいれば、それは家族の物語だ。プロフェッショナル像を、一人のキャリアの物語として捉えることはもはやナンセンスだろう。
ミレニアル世代は、性別で役割分担を決めようとは考えない。一人の成功を家族が支えた。そんな昔ながらのマスコミ好みのストーリーの話は、ナンセンスになってしまったのだ。
例えば、パートナーとの二人双方が、仕事が大好きで、出来れば海外で仕事をしたいと考えていたとする。ただ二人とも子供も欲しい、育てたいと思っているとしたら、どの国のどの都市で働くのか、どちらが譲り、どちらの意向を尊重するのか。一回一回真剣な対話と計画が必要になる。一人一人の仕事の状況や変化に応じて、柔軟な戦略が必要になると言えるだろう。
前出した雑誌Kinfolkでは、例えばこのような記事が掲載される。デンマークのコペンハーゲン出身のデザイナーとイタリアのペーザロ出身のデザイナー。結婚して一緒にデザイン会社を立ち上げている。その際、いかにして互いの故郷の二拠点での生活と仕事を実現し、子供を育ててきたか。こうしたトピックは、日本のブロガーの世界でも、「世界級ライフスタイルの作り方」の「キャリアの下り方」と題された記事、ちきりん氏がイクメンのあり方を書いた記事などで提起され始めている。
必要なのは、「計画された偶発性」の考え方だ
では、心から大切にしたいと思うことを犠牲にせずに、プロフェッショナルとして望む道を歩むにはどうしたらよいだろうか?ヒントとなるのは、「計画された偶発性」の考え方だ。
「計画された偶発性」理論とは、「個人のキャリアの8割は予想しない偶発的なことによって決定される」という主張で、スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授が提唱したもの。その予期せぬ出来事や出会いをただ待つのではなく、その転機に上手く気づき、活かせるように戦略を持って、自身の毎日をマネジメントしていこうとする考え方だ。
そこにあるのは、「緻密に計画し、予定通りのキャリアステップの実現を目指す」従来のプロフェッショナル像とは真逆の戦略だ。どの会社で何年働き、いつMBAを取得し、いつ起業するというような予定調和のキャリアプランの考え方ではないのだ。
こうした動きに呼応して、組織も変わり始めている。「社員をサーフィンに行かせよう」の著書で有名なパタゴニアが象徴的な例だろう。「社員をサーフィンに行かせよう」の意味するところは、「計画された偶発性」に対応できるマネジメントと戦略だ。
サーフィンの世界では、「来週の土曜日の午後4時から」などと、予定を計画することができない。良い波が来ているとしたら、それがタイミングなのだ。いつ来るか分からないその波に乗るためには、日々の生活と仕事とをフレキシブルにマネジメントすることが不可欠だ。さもなければ、とてもサーフィンになど出かけることはできないだろう。
それは後退ではなく、昇華である
仕事は一朝一夕には完結しない。長く長く続いていく日常だ。もし仕事の先に描かれた目標や理想があるならば、なおさら長い道であってしかるべきだ。時には夜遅くまで猛烈に働く。しかし時には休む。何週間も。何十年も走りたい、と願うならば、それこそが正攻法ではないか、と思う。
自身の内面を掘り下げようとすることは、一歩間違えば自身を大きく傷つけることになりかねない。内省の結果、自意識が肥大化して、自分では手に負えないほど虚栄心が膨らみ、逆に日々の生活を純粋に楽しむ気持ちさえ消え失せてしまうかもしれない。
しかし、忙しさに身を委ねてみても、乾ききってしまった感性からは、心を打つ仕事など生まれないのではなかろうか?生きることに真摯であればこそ、その道は険しいに違いない。仕事に生活を重ね合わせるワークスタイルは、実に難儀だろう。しかし、それは後退ではなく、昇華なのではなかろうか?それは実に高度なマネジメントと戦略を必要とする道であるからだ。
時に自分に正直に、わがままに
私は、昨年の一年間をImpact HUB Tokyoで過ごし、様々なメンバーが新しい仕事にチャレンジし、時に飛躍し、時に挫折に苦悩する姿と隣り合わせの毎日を送ってきた。明るい部分だけでなく、暗い部分をも多く目にしてきたとも思う。
しかし不思議なことに、コミュニティの担い手として、ますますエネルギーがふつふつと湧き上がってくる不思議さを発見するのだ。
2016年の世界が、好奇心と愛情に満ちた世界であってほしい。そのために、私たちは時にわがままであるべきではないか?自分が、心から大切に思う人や信念のために生きるプロフェッショナルであること。そんな生き方こそが、多くの人に伝播して花開いてくことを、願ってならない。
(冒頭写真:Photo by Diego Frangi)
この記事の執筆者
- Impact HUB Tokyo Investor Relations担当。慶應義塾大学を卒業後、大和証券株式会社にて個人投資家向け営業を担当。2013年にはImpact HUB Tokyoを通じてSOCAPに参加。社会的投資の分野に深い関心を持ち、2014年には国際協力NPO/Acumenの大阪支部であるOsaka+Acumenの立ち上げを主導。2014年末に大和証券を退職後、2015年2月よりImpact HUB Tokyoに参画。SOCAP Japan Teamプロジェクトをリードしている。
この執筆者の最近の投稿
 2016.01.14働き方ミレニアル世代が求める理想の働き方とはー変容するプロフェッショナル像
2016.01.14働き方ミレニアル世代が求める理想の働き方とはー変容するプロフェッショナル像 2016.01.04インパクトインパクト投資から組織開発まで。新年を迎えた起業家が読むべきSSIR記事10選
2016.01.04インパクトインパクト投資から組織開発まで。新年を迎えた起業家が読むべきSSIR記事10選 2015.12.19組織上場目的のスタートアップは、もう古い?ー時代の先をいくキックスターターの経営
2015.12.19組織上場目的のスタートアップは、もう古い?ー時代の先をいくキックスターターの経営 2015.12.12投資グローバル企業のCSR【後編】投資で行うCSRー企業ベンチャーフィランソロピーとは
2015.12.12投資グローバル企業のCSR【後編】投資で行うCSRー企業ベンチャーフィランソロピーとは