皆様、大変ご無沙汰しました。
ついに3日前、人生二度目の修士論文を完成して提出しました。
最後の1週間は、文字通り、朝起きた瞬間から夜寝るまでずーっと論文で作業している状態でした。
そして印刷に出してついに提出。
提出後のまる2日間は昼・夜といろんな方(MBAの学生から教授まで)とお会いしてお食事した以外は、
10時間寝たり、ラテン系とクラブに踊りに行ったり、マンガ読んだりと自堕落な生活。
流石にそろそろ社会復帰したくなったので、まずはブログからはじめることに。
最初はまず、今回の修士論文を書いていて、経営・ビジネス分野の研究をするのに大事なお作法を、
自分への覚書としてまとめておこうと思う。
文系全般の研究について言えると思ったので、こういうタイトルにしたけど、
経営・ビジネス分野のローカルルールもあるかもしれないし、逆に理系研究にも役立つし、
そもそも仕事全般に当てはまるようなこともあると思う。
1. Bibliography(参考文献集)を常に更新・メンテナンスする
経営の研究を始めたころは、何故これがそんなに大切なのか全くわかっていなかった。
Bibliographyとは、理系で言うところのReferenceと同じで、論文の一番最後に載ってる文献集のことだ。
今の研究を始めた数ヶ月前、私の先生はことあるごとに「Bibliographyを見せろ」と言っていた。
で、当時は余り理由も分からず、仕方なく書いて送っていた。
で、ウチの教授に限らず、色んな先生と話しているうち、文系の研究では、ある一定レベルの先生達は
「Bibliographyを読めば、その人がどんな背景を元に、何を書こうとしているか大体分かる」し、
「Bibliographyの内容で、その人がどれくらいちゃんと調べてるかがわかる」
ということが、わかってきたのだ。
理科系と違い、経営やビジネス分野では、過去に同じ問題意識やテーマで研究が進められていることも多く、
そこで新しく研究をする価値は、同じ問題に違う方向から光を当てた、だったりすることも多々ある。
(例えばみんなの大好きなクリステンセンの「イノベーションのジレンマ」で書かれてることの大半は、
1980年代からの研究者が言ってることと大差ない。
彼の価値は、それをディスクドライブ業界で精細に検証し、掘り下げたことなのだ。)
こういう過去の研究を踏まえたうえで新たなことをやってるんだ、というのを明確にするためにも、Bibliographyは大切なのだ。
また、多くの理系分野と違い、言葉などが体系化されてない文系の分野では、
その分野の「共通言語」を理解している、ということを示すためにもBibliographyが大切だったりする。
更に、文系の研究では、新聞やデータベースを含む文献リサーチが重要になることが多い。
こういうものも、どれだけ広範に、ちゃんと調べてるか、Bibliographyを見れば分かる。
論文を評価する側の都合だけでなく、書く側も、本や論文を読むたびにBibliographyに加えておくと、非常に便利だ。
あとで「あの本なんだっけ・・・」と思ったときにすぐに見返すことが出来るし、いざ論文を書こうと思ったときにも重宝する。
と言うわけで、文系分野で研究をはじめようと思ったら、自分が読んで参考にしたいと思った論文や本をBibliographyにしっかり整理しておくのが、まずやるべきことだ。
2. 研究内容が決まったら、その分野やキーワードで書かれた博士論文・修士論文を探して読む
私が指導教官に、まず最初に読め、といわれたのが似た問題意識で研究している過去の博論・修論だった。
これは文系に限らず、理系でもはじめてその分野の研究をしようと思ったときに非常に役立つと思う。
特に、博士論文が素晴らしい。
博士論文は、その分野で身を立てようと思った人が、基礎から自分の理論なりを打ち立てるため書くものだ。
通常、教科書に書いてあるレベルから、最前線の研究に至るまではギャップがあることが多いが、
博士論文にはちゃんと基礎的なことから、研究の進め方、読むべき基礎文献も含めてちゃんと解説してある。
また、修士論文と違い、厳しいディフェンスも通ってるので、ある程度の質も確保されている。
(修士論文はレベルがまちまちであることも多いのは、日本もアメリカも一緒。
ただ、経営・ビジネス分野は修士論文でも質の高いものが非常に多い。
普通の修論と違い、社会人だとか他分野の研究者を何年も続けた後に書いてる人が多いからかも。)
従って、その分野ではじめて研究しよう、という人には絶好の指南書なのだ。
色んな大学の過去の博士・修士論文は、Google ScholarやD-spaceで簡単に検索することが出来る。
3. 指導教官の期待値をうまくコントロールし、自分が指導を受けやすいように調整する
私は社会人になる前に大学院で研究していた頃は、こういうことを考えたことが一度も無かった。
指導教官というのは、学生のために時間をちゃんと使い、指導をしてくれるものだと思っていた。
それが出来ない指導教官というのはダメな教官なのだ、と思っていた。
ところが、社会人になってから、社会はそうは動いていないことを知った。
例えば、自分のやっているプロジェクトにどうしても上司の協力を得なければならないときは、
どんな手を使ってでも(笑)上司の注意を喚起し、時間をもらえるように努力する。
上司があまりにも詳細まで入ってきてやりにくいときは、早く上司を安心させて手を引かせ、
自分が一番動きやすいように調整する。
上司が特に自分のプロジェクトを最優先に考えてないのは、世の中では当然であり、
その上司の期待値をうまくコントロールし、一番活用するにはどうするか、という身の処し方を社会人は学ぶわけである。
学生の時に、こういうことに気づく人はまれかもしれないが、指導教官も同様なのだ。
まずは、自分は指導教官に対して、どういう指導を受けることを期待しているのか、を自分の中で明確にするのが大切。
指導教官の性格を把握することも大切だ。
その上で、理想的な指導を受けるにはどうすればいいのか、指導教官との付き合い方に戦略を持つ。
(本来は、指導教官を選ぶ際にも、こういう視点で見るのが良い)
指導教官が、もしマイクロマネージが好きで、細かく学生の研究に手を入れたいタイプの場合、
かつ、それが面倒でイヤだ、と感じる場合は、出来るだけ早い段階で、大枠を提示して、
相手を安心させて、手を入れさせ過ぎないようにするのも一つの手だ。
逆に指導教官が、余りにも放任主義の場合は、どうやって注意を向かせるか考えなくてはならない。
リスクはあるが、全然出来てないことを見せて、不安にさせるのも一つの手である。
指導教官がルーズで、言ったことを全然やってくれない、という性格なら、
ミーティング時間を出来るだけ長く取り、問題は全てミーティングの中で解決するようにする。
(で、教授がそれ以外の時間に時間を使って解決してくれるとは期待しない)
それ以外のお願い事は、口頭だけでなく、メールで送ったり、秘書を活用するようにする。
指導教官が、どうしても自分の指導に熱が入っていないと思うとき。
何が彼・彼女の今の一番の懸念事項なのか考え、それを解決して、注意を自分の研究に向かせる必要がある。
次の研究予算がいくら取れるかとか、担当している授業の方が、学生の研究よりも余程大事な瞬間も、彼等にはあるだろう。
それに対して、ある程度の理解を示し、解決に協力して、自分の研究に注意を向かせることも大切だ。
指導教官は、自分より専門知識も経験もあるが、一人の人間なのだ、という事実を受け入れて、
どうやったら一番自分の研究に役に立ってもらえるのか、という発想で考えるのが良い。
もっとも、指導教官がそれ以上に、人間的に、自分に与えてくれる影響は沢山あるだろう。
でも人間的にどんなに素晴らしくても、自分の研究にも役に立ってもらわないと困るわけで、その方法は戦略的に考えるべきなのだ。
4. 自分が何の問いに答えたいか明らかにする→答えの仮説を立てる→それを検証する方法を考える
これも、理系・文系に限らず、研究を効率的に進める上で非常に大切なことだ。
コンサルティングファームに勤めて、こういうことが当たり前に出来るようになってから、研究の世界に戻り、
初めて、研究をする上でも非常に大切なプロセスなのだ、と言うことが分かった。
まず、自分の研究が、どのような問題に答えるためのものなのか、を明確にするのが大切だ。
これが明確に定まってないと、何のための研究だか分からなくなるし、軸がブレやすくなる。
これをコンサルの言葉ではIssue Identification、と呼ぶ。
研究に限らず、会社などの全てのプロジェクトでも非常に大切で、
「一体何を解決するためのプロジェクトなのか」を明確に定めて常に意識しておくことで、ぶれずに進めることが出来る。
次に大切なのは、その問いに対する解の仮説を立ててから、検証計画を立てることだ。
これをやると、闇雲に文献やデータを調べなくても、その仮説の検証に必要なデータだけを調べれば良くなるので、非常に研究の効率が上がる。
5. 出来るだけ沢山の人と議論して、インプットをもらう
新規性が大切で、人に話すとアイディアを盗まれてしまう、というわけでない限りは、
出来るだけ沢山の人に話を聞いてもらい、インプットをもらうことは、研究の質を上げるのに非常に重要だ。
こうすることで、「自分の研究に足りない視点は何か」「自分の研究が学界にどれだけのインパクトを与えそうか」などを事前に把握することが出来るし、
議論から新しいアイディアが出てくることもある。
指導教官だけが、研究を指導する人ではない。
同じ大学の先生であれば、多くの場合喜んで時間をとってくれることは多いだろうし、
他大学の先生であっても、その先生の研究分野に関連があれば、話を聞いてくれるだろう。
そして、こういうネットワークは、もしその研究分野で身を立てるとなった場合、
例えば何かのポストについたりするときに推薦者が増えるわけで、色んな意味でプラスなのだ。
ただし、指導教官をちゃんと立てて、事前に他人に話を聞いてもらうことは知らせたり、
指導教官を介して紹介してもらう、のは人間として当然の礼儀である。
6. とにかく書く-モノがないと始まらない
指導教官の指導を仰ぐ際も、いろんな人のインプットを受ける際も、何か見せるモノがある、のは重要。
ポスターでもいいし、プレゼン資料でも良いし、論文の概要でも良い。
何か、アイディアがあったら、たたき台になるような資料をいつでも作っておくこと。
自分の研究が完全に進んでいるわけでなくても、1で書いたBibliographyがあるだけでも、
文系の場合はかなり有効なようだ。
また理系の場合は、実験データとか、計算結果とか、まだ文章にはなっていなくても、
最低限の議論が進められるような資料を、自分なりにまとめておくのは重要だ。
とりあえず、今思いつくのはこれくらいだろうか・・・
まだ他にもある気がするので、思い出したらコメント欄か、第二段で書きます











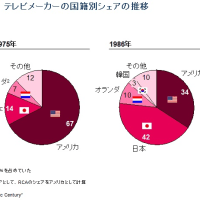
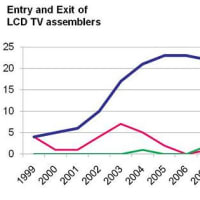
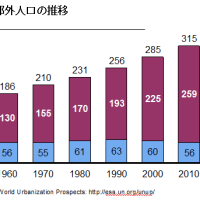
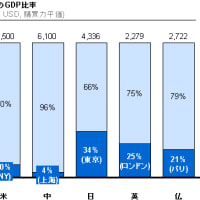

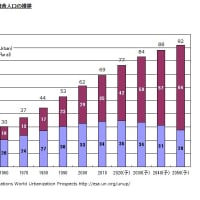
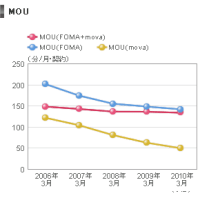
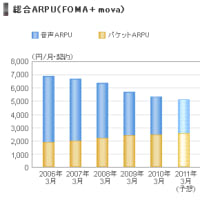
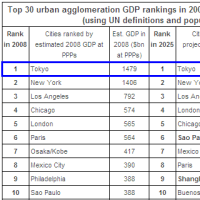
Outputをすることで自分の考え方がまとまることがあるし、そういうことをするプロセスで他の1-5が生きると思います。研究者は毎日物書きをずっとしていないければならないというのがよく分かる。その中で、可能な限りの輝いたネタだけを拾い出し、それを論文にするのが良いのではないかと思います。
気づけば、計算ノートよりも計算したノートから結果を拾い、自分が何をしたかをノートにまとめている時間のほうが圧倒的に多い気がする。そうやって毎日前進するのだなぁ・・・って、個人研究者みたくなってから(それも一つの指導教員との付き合い方だと思っていますが)、それが一番重要なんだと思いました。
タイトルは、「文系の研究論文をはじめて書く方のための覚書」ってなってますけど、これは分野に関係ないと思います。理系ならではのところは一切ないと思いますよ(今なら、膨大な文献が理系にもたくさんあります。今はどこの分野も顔を知らない人が出てくるほど多くなってしまったので、やっぱり文献情報に頼らざるを得ないのだと思います。そうすると、常にそれを最新のものにしておくことは重要だと思いますし、自分自身はあまり公開したくない情報ですね。何を考えているかばれるから(笑)あれこそ、自分の研究の宝なのだと思いますよ。)
はっきりいって自己啓発セミナーです笑
アメリカの大学のMBAマーケティングですね。
そう、それでどれだけのオリジナリティを加えられたかを見る、というのと、ちゃんと勉強してるかを見る、という効果があるのかな、と思いました。
後者は理系にいた時は余り無い感覚だったので、新鮮でした
@Mameoさん
かなり理系にも当てはまりますよね。
まあ「理系にも当てはまる!」とおおっぴらに書くと、「当てはまりません」という人が必ず出てきてうるさいので(笑)こうしたわけですが。
>今なら、膨大な文献が理系にもたくさんあります。今はどこの分野も顔を知らない人が出てくるほど多くなってしまったので、やっぱり文献情報に頼らざるを得ないのだと思います。
参考になります。
一般に成熟産業に達した研究分野ほどこうなりがちだとは思うのですが、
理系も色々ありますが、バイオ系の友人に聞くと、バイオ分野もいまやそうであると聞いて、隔世の感がしました。
@くまさん
>MBAって転職するとき以外に何の役にも立ちませんよ。MBAとって妙にプライドが高くて使いずらくてしょうがないやつがたくさんいる
そう、こういう偏見が数々あるからこそ、MBAをどう過ごすか、というのが非常に大切だと思います。
MBAに行くことでかかるコストだけでなく、こういう偏見を明らかに上回る経験と能力をつけてないと、損ですからね。
なるほど、と思った方は是非、下記の記事を参照してください。
http://blog.goo.ne.jp/mit_sloan/e/398f622849358322754903f37acc9586
http://blog.goo.ne.jp/mit_sloan/e/858fe7ad5a850186fb8f7aa379eb2777
これだけわかっているのならLilacさんなら
大丈夫でしょう。
てかこのブログ最近見つけたんですよ。
Lilacさん才色兼備ですね。
写真見たらめちゃくちゃ美人だし!
上でもコメントされていますし、その返事にもありますが、今回の記事の内容はすべての研究に当てはまるような気がします。というか、「バイオ分野もいまやそう(=昔はそうではなかった)」というのが信じられません(私はバイオ系の研究者ではありませんが)。
修士論文提出おめでとうございます!
そして本当に本当にお疲れ様でした。
このブログを通して多くの方が留学の醍醐味を学んだのではないでしょうか。
今回のポスト、非常に面白いですね。
私は学部生ですが最終学年に向け参考に(特に博士課程の論文)したいと思います。
それにしてもBibligoraphyの重要性は理系と文系でそんなに違うのか…未知の世界です。
以前tweetしたのですが、おそらく届いていないと思いますので勝手ながらこちらに書きこませてくださいね。
感情を抜きにできる人間はいませんよね。ロボットや自然界に(映画等)感情作らせるくらいだもの。自分のあほなブログで、1人でもありがとう、元気出たと言ってくれる人がいれば私はにんまりです。Lilacさんの「お疲れ様!」嬉しかった。http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/0419/309359.htm?o=0&p=1
写真で騙されないように注意してください(爆)
@Siuyeさん
バイオ系と言っても色々あるので一般化すると誤解を生みそうですが、
分野によっては、Referenceはもちろん大事ですが、書かなくても分かってるほど狭く、かつそんなに先行研究が無い分野だったのが、今はそうではなくなってる、という話を聞いたわけでした。
@かばんさん
自身もブロガーであるかばんさんに言われると光栄です。
こちらこそいつも読んでくださって有難うございます。
理系(物理)にいたときは、Bibliographyはここまで大切にはされてなかった-少なくとも頻繁にちゃんと更新しろ、みたいなモノではなかった気がしました。
まあ分野によるのかもしれませんが・・。
理系でも先行研究が沢山あって、いわゆる文献研究がより重要な分野では、大切になるかもしれません。
TweetはTwitter自体やAPIのせいで届いてなかったり、時には大量に届いて私が読めていなかったり、
読んでるけど返事を返してないことも多々あります。
でも一つの言葉が正の感情を皆にもたらせるとしたら嬉しいですね。
私自身、コミュニティカレッジにて勉強しておりますが、Bibliographyを作成する意味がわからずとりあえず提出しておりましたが、このブログを読んだ時には目からウロコでした。。。
これからのブログも楽しみにしております。乱文失礼しました。
客観的に事実を把握するのは、簡単なようで難しい時が多々あります・・・。進化の流れは何処に向かっているのでしょう・・(?)